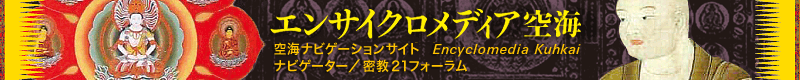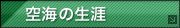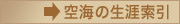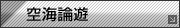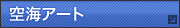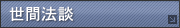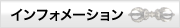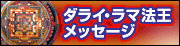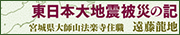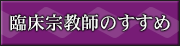ソロトークにつづき松岡氏は長柄師をステージに招き梵字・悉曇について聞く。デモンストレーションに時間を配分するため、長柄師への質問は梵字に関する基礎的なことであったが、
長柄師は来場者にわかりやすく答えられていた。つづいてデモンストレーションに移り、この模様をテレビカメラがステージ上のスクリーンに映し出した。
ソロトークにつづき松岡氏は長柄師をステージに招き梵字・悉曇について聞く。デモンストレーションに時間を配分するため、長柄師への質問は梵字に関する基礎的なことであったが、
長柄師は来場者にわかりやすく答えられていた。つづいてデモンストレーションに移り、この模様をテレビカメラがステージ上のスクリーンに映し出した。
さて梵字・悉曇とは、パーリ語あるいはプラークリット語(俗語)で書かれた時代を経て、仏教経典の多くはインド古代の文語であるサンスクリット語で編纂され、 当然のことながらサンスクリット語の字体(書体)で表記されていた。現在私たちは、仏典の多くを文法のよく整備された 「古典サンスクリット語(Classical Sanskrit)」と「デーヴァナーガリー(文字)」と言われる書体によって出版されたテキストで読むことができるのだが、 空海が長安で出会ったインドの文字は書体を少し異にするものであった。
 空海は、たぶんまちがいなく、当時の長安にもたらされていたサンスクリット語を習得し、サンスクリット語で書かれたmade in Indiaの仏典をたくさん閲覧し、
相当に読めて書けたに違いない。さらに訳経家の指示に従ってサンスクリット文字を毛筆あるいは刷毛筆(木や竹を細く裂いたもの)で書写する中国人書写生の書法をその目で見、
空海らしい文字への強い関心をフル回転させ、練習しては自分のものにしたことは想像に難くない。
空海は、たぶんまちがいなく、当時の長安にもたらされていたサンスクリット語を習得し、サンスクリット語で書かれたmade in Indiaの仏典をたくさん閲覧し、
相当に読めて書けたに違いない。さらに訳経家の指示に従ってサンスクリット文字を毛筆あるいは刷毛筆(木や竹を細く裂いたもの)で書写する中国人書写生の書法をその目で見、
空海らしい文字への強い関心をフル回転させ、練習しては自分のものにしたことは想像に難くない。
「梵字」とは一般にサンスクリット語の文字を筆で書いたもののことを言うようであるが、厳密には、空海が長安で学びとってきたサンスクリット語の書体である、と言うべきであろう。 その梵字の書き方や文字と文字のつなぎ方などを約束ごとに従って書く書法・筆法のことを古来日本では「悉曇(しったん)」といっている。
この「悉曇」はことに真言宗の僧侶の必修科目であり、真言・陀羅尼を唱えることと同様「声字実相」に込められた空海の密教思想の根幹をになう実学・実修だけに、 その正しい理解と気迫のこもった書き方そして字形の上手下手は真言僧侶にとって一大事なのである。

 今回、澄禅流悉曇の阿闍梨であり、ベナレスサンスクリットカレッジに留学された経験をもつサンスクリット学者、高野山真言宗光恩寺住職・長柄行光師にお願いし、
梵字のカリグラフィーデモンストレーションをお願いしたのだが、師は、会場にて、「kobodaisi(こうぼうだいし)」「samudra(海)」
「huum(フーム・うん・吽)」などを書いてくださり、またアドリブでゲストの浅葉克巳氏の「ASABA」を一文字にして書いて見せてくれた。
今回、澄禅流悉曇の阿闍梨であり、ベナレスサンスクリットカレッジに留学された経験をもつサンスクリット学者、高野山真言宗光恩寺住職・長柄行光師にお願いし、
梵字のカリグラフィーデモンストレーションをお願いしたのだが、師は、会場にて、「kobodaisi(こうぼうだいし)」「samudra(海)」
「huum(フーム・うん・吽)」などを書いてくださり、またアドリブでゲストの浅葉克巳氏の「ASABA」を一文字にして書いて見せてくれた。
このデモンストレーションから、一つの作品にさまざまな書体が混在する空海の書法の特徴「雑体書法」や「合体書法」に、あるいは「飛白体」の書法に、梵字の筆法が諸所に認められ、 漢字さえも空海の精神上は梵字つまり「真言・マントラ」に等しく、さらに言えば空海が書く一文字一文字は「法マンダラ」としての一文字一文字という密教世界なのだということが強く感じられた。
長柄師のパフォーマンスを目の前で見た来場者の感想は、「話で聞くだけではいまひとつ理解できないことが、きょうは梵字独特の「切り継ぎ」など実際に書いているところを 見せていただきながら、完成した文字の意味の説明もあり、梵字の意味の深さがわかりました」に集約されました。