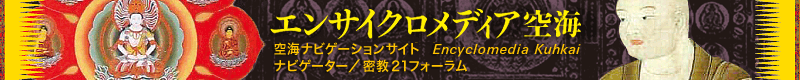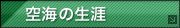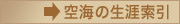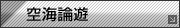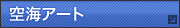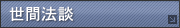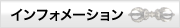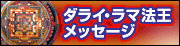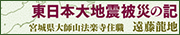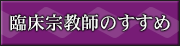空海の密教は、他の宗派と異なり教理の学習にとどまらず、修禅観法による真理の神秘直観にあるため、それに適した場所が重要になります。密教の諸経典によると、それは人里離れた幽玄閑寂な山野であることといわれています。
空海の密教は、他の宗派と異なり教理の学習にとどまらず、修禅観法による真理の神秘直観にあるため、それに適した場所が重要になります。密教の諸経典によると、それは人里離れた幽玄閑寂な山野であることといわれています。
空海は唐から帰朝するとき、密教流布の根本道場の地を示せと祈念し、持っていた三鈷杵[さんこしょ]を明州の浜辺から飛ばしました。
帰朝後、その三鈷杵を探し出す旅に出かけ、大和国宇智郡で、黒白二匹の犬を連れた、身の丈八尺ばかりの赤ら顔の異様な猟師に出会い、三鈷杵が高野山にあることを耳にします。この猟師は高野山の地主神の狩場明神[かりばみょうじん]なのです。
このあと、空海は紀州の境で一人の山人、丹生明神[にうみょうじん]に逢います。
この明神につきそわれて到った山中は鉢を伏せたような地形で、周囲には八つの峰が聳え[そびえ]、巨大な桧が竹林のように並び、そのうちの一本の桧の股に唐で投げた三鈷杵が突きささっていました。
空海が奈良の都に上がった青年のころ、山野を跋渉し、吉野から南へ一日ほどさらに西へ二日ほど歩くと、山頂に平原の幽地があり、これが紀伊国伊都郡高野山だといわれています。
年経て、空海四十三歳のとき嵯峨天皇にこの高野の山を賜りたいを上奏します。その理由として、一つに国家のため、二つに修行者のために根本道場を築くこと。この上奏に勅許が下り、空海は弟子の泰範、実慧を遣わし、更に山上に伽藍建立のため七里四方と壇場を結界します。
空海は入滅するまで、高野山を修行者のための入定の地と定めて開創に着手します。そしてここ高野山は空海自身の永遠の入定の地にもなります。
 ◎金剛峯寺と名づけられたのは「金剛峯楼閣一切瑜伽瑜祇経[こんごうぶろうかくいっさいゆがゆぎきょう]」により、宗教的な瞑想をする者の寺院という意味です。
◎金剛峯寺と名づけられたのは「金剛峯楼閣一切瑜伽瑜祇経[こんごうぶろうかくいっさいゆがゆぎきょう]」により、宗教的な瞑想をする者の寺院という意味です。
◎空海の在世中に完成した建物は講堂と僧房で、多宝塔(大塔)は半分でき上がっただけで完成しませんでした、いかに高野山の開創が難事業であったかがわかります。
◎狩場明神、丹生明神が空海に高野山を提供したことは神仏習合を物語ることになります。また丹生とは水銀のことで、空海はこの水銀鉱脈も得たことになります。