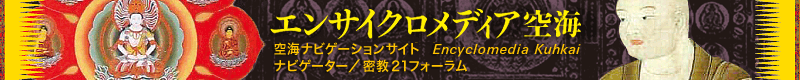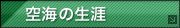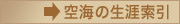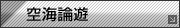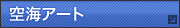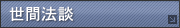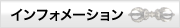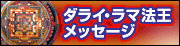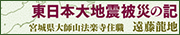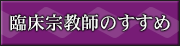これを何とか解決しようと諸仏に祈念します。するとひとりの僧が夢枕に立ち「大毘盧遮那経[だいびるしゃなきょう]」(大日経)の所在を教えてくれたと いいます。これが久米寺の大日経でした。探し求めた空海は言語に絶する研究を続けますが、理解できず、問うても答えてくれる者がいません。そこで正嫡の純 粋密教を学ぼうと入唐を決意します。

一方、桓武天皇の厚い帰依を得て内供奉[ないぐぶ]に任じられていた最澄(三十八歳)は天皇の詔を受け、遣唐大使藤原葛野麻呂[かどのまろ]、副使菅原清 公と共に摂津の難波を出発しましたが、暴風雨のため九州にとどまります。そして翌年、第二船に還学生[げんがくしょう]として遣唐船に乗ります。
名もない私度僧であった空海(三十一歳)も、阿刀大足か佐伯今毛人[いまえみし]の縁故からか東大寺戒壇院で具足戒を受け、留学生[るがくしょう]として、葛野麻呂や橘逸勢[たちばなのはやなり]と共に第一船に乗ります。
途中四隻の船は未曽有の大暴風雨に遭遇し、第三船は引きかえし、第四船は行方がわからなくなり、一ヵ月ほど海上をただよい、九死に一生を得て空海は唐の福州赤岸鎮に、最澄は明州寧波府に漂着します。
◎この未曽有の航海は空海にとって経験したことのない最大の修行であったかもしれません。しかし、すでに宇宙の営みを知った空海は船倉にいて大きな目を輝かせ結跏趺坐[けっかふざ]し、口唇の端にうっすら微笑を浮かべていたかもしれません。